2024年SDGs週間 サステナ座談会
株式会社横浜八景島は『ほほえムービング』と称し、さまざまなサステナ活動を実施しています。
今回、当社は『ほほえムービング』の一環として、初の試みとなる『SDGs座談会』を開催いたしました。
毎年9月末からはじまる『SDGs週間』にあわせて開催されたこの座談会では、市都市経営局理事・温暖化対策統括本部長として横浜スマートシティプロジェクトなどを推進された信時正人さんを迎え、当社の活動の意味を振り返るとともに、活動を未来へつないでいく大切さについて考えました。
私たちはこれからも、地球環境の保全に貢献するために「ほほえムービング」を推進して参ります。
「すべての生きものがかかわる地球環境を守ることに貢献する」をコンセプトに、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティアクションに取り組む株式会社横浜八景島。働くすべてのスタッフがこのアクションに積極的に参加し、多くの方と協働・共有することで未来の地球環境を守っていくことを目指しています。
持続可能な社会の実現に向けてどう取り組んでいくか、横浜八景島の国内6施設のサステナビリティ活動担当者が、横浜ブルーカーボン事業を推進してきた信時正人さんに現状や課題を聞きながら議論を交わしました。
合言葉は「ほほえムービング」

株式会社横浜八景島
経営企画部長
奥津 健司
1992年に株式会社横浜八景島に入社し、飼育担当に。八景島シーパラダイス開業時から海の動物たちのショーに出演。ふれあいラグーンのチームリーダーなどを歴任。アクアリゾーツ館長などを経て、2021年から経営企画部部長として飼育戦略やサステナビリティの推進などを担う。
― 初めに取締役執行役員でサステナビリティ担当部長の奥津さんから、横浜八景島のサステナビリティ活動「ほほえムービング」が生まれた背景についてご説明をお願いします。
奥津
西武グループでは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして「サステナビリティアクション」を行っています。私たち八景島の従業員一人ひとりが、グループのサステナビリティアクションを進めるために、自分事として考え、行動をするためにはどうしたらいいのかということで、名称とロゴを作って、皆さんに意識を高めてもらおうと考えました。
「ほほえムービング」と名づけたのは、西武グループのスローガンが「でかける人を、ほほえむ人へ。」、横浜八景島のスローガンが「生きものを通じて世界に笑顔と感動を」で、どちらも「笑う」というキーワードが入っています。「ほほえみ」ということと、今の私たちの行動、活動が未来を変えることができる、動かすことができるということで、「ほほえむ」とムービングを合わせて「ほほえムービング」にしました。皆さん一人ひとりが自分事として活動していきましょうという思いを込めた合言葉です。
―カラフルな色合いが印象的ですよね。
奥津
そうですね。SDGsの17色を意識しました。会社としてサステナビリティについて動き出したのが2021年からです。ロゴは2022年に作成しました。SDGsが採択された9月25日を含む毎年9月末の約1週間、持続可能な開発目標(SDGs)の推進と達成に向けて意識を高め、行動を喚起するイベントが世界各地で行われていますが、それに合わせ、横浜八景島でもSDGs週間として様々なサステナビリティアクションを実施しています。
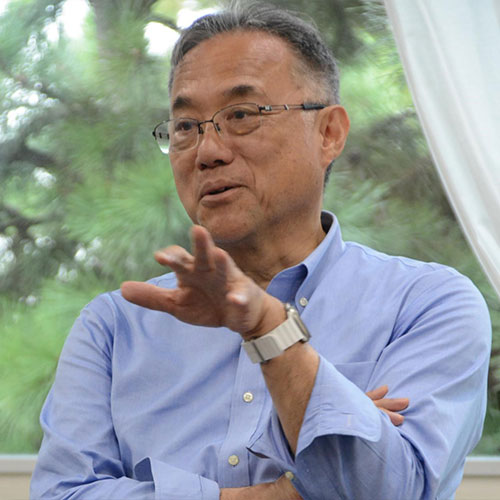
信時 正人さん
市都市経営局理事、温暖化対策統括本部長として横浜スマートシティプロジェクトなどを推進。現在は㈱エックス都市研究所理事、神戸SDGsユニットユニット長、前ヨコハマSDGsデザインセンター長。
サステナビリティとは?
―それでは信時さん、サステナビリティとは何か、改めてご説明いただけますか。また、サステナビリティは現在どのような方向に向かっていってるのか、その辺りをお聞きしたいと思います。
信時
「サステナビリティ」という英語なんですが、日本語でいえば「持続可能性」。いかに続けていけるかですよね。例えば会社の寿命は30年といわれていますが、50年、70年、100年続けていくにはどうすればいいかを考えて、色々と工夫しますよね。そういうシンプルな話なんです。
今までのように一回使って終わり、というか、例えば燃やして終わりとかではなくて、いかに古いものをもう1回使えるかとか、リサイクルするとか。できるだけ地球の資源を使わないでやっていくことかと思います。僕らのベースは地球になりますが、現在、人間の活動は地球2個半ぐらいの資源がないとやっていけないといわれています。地球が提供する自然の恵みとか食料とか、今の人間の生活からいうと、足りない。ですから、継続するためにはどうすればいいか、今ある状態をどうやったら保っていけるかとかということをまず一生懸命考える。その入り口がSDGs17の目標です。これはあくまでも入口ですから、7番から始めますっていう人がいてもいいし、12番から始めるっていう人がいてもいい。ポジションや役割などから決めていけばいいと思います。

横浜・八景島シーパラダイス
河端 勉
横浜・八景島シーパラダイス 横浜ブルーカーボンはここから生まれた
―では、各施設の担当者の皆様からサステナビリティ活動の取り組みについてご紹介をお願いいたします。
河端
海がそばにある立地を生かしてワカメの植え付け・収穫に継続的に取り組んでいます。また、海育をテーマにした「うみファーム」でお客様に参加していただいて、ブルーカーボンや未利用魚の利用、海洋環境についてお話しするプログラムを実施しています。今年9月のSDGs週間でも色々な取り組みを実施したのですが、サステナの担当者が昨年の2人から7人に増え、色々取り組む体制ができてきたと思います。
また、水族館として繁殖の取り組みもしています。今年の夏にバンドウイルカが3頭誕生し、ふれあいラグーンではお客様の前で繁殖の取り組みについてお話しするなど、新しい取り組みや、色々な発信の仕方ができるようになってきたと思います。
―小さなお子さんの反応はいかがですか?
河端
小学生や保育園のお子さまたちは、最近サステナの話にふれる機会が多いようです。うちの小学生の娘もそうなのですが、家に帰ってきて話を聞くと、学校でサステナについて話があったと。子どもながらに興味はあるんだなと感じています。課題として、ワカメの植え付け・収穫など、サステナの活動をしていますが、このまま毎年継続しながらもその取り組みをどう発信していけばいいのか。参加された方がサステナについて知って、持ち帰って、それが何かにつながっているのか、そんなに広がりもないのかなという部分も感じています。今後どういう進め方をすればよいのか、まったく違ったことを始めるべきなのか、という疑問はあります。
信時
ワカメの植え付け・収穫を始めた当初、300人ぐらいのお子さんに来ていただいてやってもらったんですね。お湯に入れた瞬間一気にワカメが鮮やかな緑色になった時、子どもさんはおろか、若いお父さんやお母さんが驚いていました。そのときに、食育が必要なのではないかと思いました。日本全国で目の前に海があるのに、目の前で獲れた魚や海藻を食べられないという状況が続いています。海の近くに住んでいるということを忘れているし、恩恵を感じていない。目の前で獲れるものを食べられるようになると、意識が変わってくると思うんです。 そういう発想を発信していく拠点に、八景島シーパラダイスはなるのではないかと思います。
奥津
食育の話がありましたが、12月に植え付けたワカメを2、3月に収穫し、給食で食べてもらうという学校と連携した新しい取り組みをちょうど企画しているところですので、今までの活動からさらに幅が広がるのではないかと思います。

マクセル アクアパーク品川
高村 直樹
マクセル アクアパーク品川 年間150万人の来場者に発信を
―ありがとうございます。では高村さんお願いします。
高村
アクアパークは、八景島や他の水族館に比べて周りに海がない環境にあります。そのため、海などの自然を使った取り組みが行いにくい施設だという実感はあります。そういう状況の中で何ができるかということを考えてきました。
例えば餌など、すでに今使っているものに目を向けてみました。今までは餌を加工した際に出る廃棄物とか、少し傷がついている餌とか、ポイポイ捨てていました。そういった場面が結構見られたので、「あれ、捨てられた餌、まだ使えるのでは?」と。なるべく使える部分は使っていかないと、将来的にもしかしたら餌にしているアジが手に入らないということもあるかもしれない。それで、最近は廃棄の基準をつけて、みんなに周知して、使える餌は捨てずにを使って、なるべく廃棄を減らそうと意識しているところです。
アクアパークは海に面していないので、八景島のように周りの海から海水を引っ張ってきて使うということができません。そのため、海水が必要な動物の水槽は、人工海水でまかなっています。しかし、調べていくうちに、もう少し節約できるんじゃないかということを考えました。そして実際の海の海水濃度をふまえ、人工海水の塩の量を減らして調整してみたら、使用する量をかなり減らすことができました。
アクアパークは多くのお客様が訪れる都心の施設なので、発信の効果が得やすい施設だと思います。子どもたちを集めた企画や、サステナ活動の発信なども2年程前から積極的に行っています。このように、現状は色々なことに取り組んでいるのですが、これから私たちは何をしなくてはいけないのか、これらの課題について教えていただきたいです。
信時
日本全体でいうと、課題はまだまだあるんですよ。日本のブルーカーボンに関する取り組みは、非常に細かく研究が進んでいるんです。例えば、海藻の種類ごとに二酸化炭素吸収量を測定しています。しかし、マングローブなどがあるアメリカやオーストラリアと比べると、日本の取り組みは二酸化炭素吸収の規模がものすごく小さいんです。きめ細かいといえばきめ細かい。でも費用対効果でいうと難しい。調査自体に多額の費用がかかりますしね。
一方で、3Dで画像を撮って、CO2の固定量を計測できるシステムが開発され始めています。こういう技術が使えるようになれば、調査にかかるコストをおさえることができます。森林がどんどん古くなってCO2吸収量が減っていっている中で、やはりブルーカーボンでCO2吸収量を増やしていくことが効果的ですよね。そのため、最新の技術を活用しながら、いかにコストをおさえ、ブルーカーボンの吸収量を増やしていくか、というところが大事になってくると思います。
奥津
他の水族館と比べると、自然のフィールドがないというのは難しい面もあるかと思いますがが、やはりアクアパークは年間150万人のお客様が来場される水族館ですので、多くの人に伝える発信力は、グループの中でも一番頑張っているのではないかと思います。最新の正しい情報をいかにお客様に伝えるかというところを考えて、さらに取り組んでもらいたいです。
また、サンゴの飼育ではグループの中でもアクアパークが積極的に活動していると思います。生物の多様性を維持する取り組みもぜひ続けてもらいたいと思います。

仙台うみの杜水族館
安部 奏
仙台うみの杜水族館 東北ならではの保全活動に取り組む
―続けて安部さん、お願いします。
安部
仙台は自然が豊かな地域なので、主に自然環境の保全に力を入れています。県内唯一の水族館という立場を生かし、行政や研究機関、地域生物保護団体などと連携しながら、さまざまな取り組みを行っています。
地域の淡水域では、希少な日本産淡水魚の繁殖・保護活動や里山のシンボリックな存在であるホタルの繁殖にも取り組んでおり、地域の研究機関や生物保護団体と連携して情報交換を行っています。東日本大震災前は、水族館周辺地域でもホタルを見る場所が多かったようですが、個体数が減少している現状から水族館の飼育下で繁殖に力を入れています。その技術は、地域の関係者にも共有され、成果を発表するなどの取り組みを行っています。また今年から、地域の研究機関と共同で震災時に失われてしまった松島湾のアマモ場の再生に向けて宮城県より採捕許可をいただき、新たなフィールドを開拓して調査や研究に取り組んでいます。
ビーチクリーン活動にも積極的に参加しており、海岸の清掃活動を行うとともに、伐採林や漂着した流木を活用し、動物飼育舎の展示レイアウトや止まり木などをつくり再利用に取り組んでおります。
石巻漁港の沖合底引網漁の漁業関係者が漁獲する深海魚の中には、今まで捨てていた未利用魚を食用として活用する取り組みを行っており、水族館内でその取り組みを紹介したり、未利用魚の対象種を飼育している生物の餌として当館も利用する取り組みを行っています。
昨年異動してきたばかりということもあり、東北地方でのブルーカーボン活動についての情報などを、信時さんがお持ちでしたら教えていただきたいです。
信時
東北ではいろいろと面白い活動がありますよ。フィッシャーマン・ジャパンという若手漁師の集まりは、自分たちで企業経営を行ったり、全国から期待が高まっています。
あと、一昨年ですかね、岩手県の洋野町が東北で唯一、カーボンクレジット(炭素排出権、以下クレジット)を申請したんです。5年間で3000トンのクレジットを申請して認可されているんですね。その年の夏に東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バッファローズ戦の試合は、洋野町で作ったクレジットでCO2を出さない試合として開催されました。
奥津
津波で失われたアマモ場の再生活動など、震災復興の象徴としても様々な取り組みをしている水族館ですので、震災で失われた生息環境を今後どう取り戻していくのかを考え、引き続き活動を続けてほしいと思います。

上越市立水族博物館 うみがたり
杉山 けい
上越市立水族博物館 うみがたり
循環型システムの構築を目指す
―次に杉山さん、お願いいたします。
杉山
当館は上越市が運営していた水族館を引き継ぎ、2018年にグランドオープンしました。サステナ活動としては、県立海洋高校の生徒さんたちと協力し、2022年からアクアポニックスという取り組みに力をいれています。アクアポニックスとは、魚を飼育する水槽の水を植物栽培に利用するシステムです。当初は、水族館内の水槽で様々な種類の植物を栽培できるか実験を行っておりましたが、現在は、県立高田農業高校と連携し、より大きな取り組みを進めています。
具体的には、水族館で廃棄される魚の餌を肥料として活用し、アクアポニックスに利用するという循環型システムの構築を目指しております。今後、取り組みをさらに発展させ、地域の学校とも連携しながら、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えております。
また、サステナビリティ活動は皆で取り組むべきものだと考えていますが、自分たちの取り組みにどれくらい効果があったのか、具体的に視覚化するのが難しいという点について悩んでいます。やっていく本当に意味があるのかなど、実感できるとさらに積極的に取り組めるのかなと思います。
信時
視覚化というところでいうと、最近注目されているのは、海水中の二酸化炭素濃度を測るセンサーです。沖縄ではこのセンサーを使って観光プログラムを開発し、観光船を運行している会社があります。サンゴ礁や藻場の近くに行くと、二酸化炭素の量が減る様子が観測できるんですよ。ただ、海藻がどれだけ二酸化炭素を吸収しているか、正確に測るのは難しいんです。海藻の種類や生えている場所によって、吸収量も変わってくるからです。
奥津
うみがたりは、行政や地元の学校などと連携しての取り組みがしやすい施設だと思います。視覚化できず成果がわかりづらいということもあるかもしれませんが、まずは水族館で出る魚の餌の廃棄量を減らすなど、自分たちで数値化できるところから取り組んでみてもよいのかもしれません。アクアポニックスを通して、環境に優しい取り組みを広げる活動は、引き続きやっていってほしいと思います。

ヒノトントンZOO(羽村市動物公園)
長谷川 珠美
ヒノトントン ZOO 羽村市動物公園 動物の排泄物や残餌などで堆肥づくり
―ありがとうございます。羽村市動物公園の長谷川さん、お願いします。
長谷川
羽村市動物公園では、毎月多摩川河川敷のごみ拾いを行っています。9月のSDGs週間では観光協会の皆さんや、市役所の職員の方々、障碍者就労支援施設の皆さんにもご協力をいただき、清掃活動を行いました。私自身参加するのは初めてでしたが、多摩川にはたばこや金属類のごみなどたくさんのごみが流れ着いていて驚きました。1時間ほどみんなで協力し、多くのごみを回収することができました。
園内ではコンポストを設置し、動物のフンや食べ残しなどを堆肥にして、野菜を育てる活動をしています。そして、その野菜を動物に与えたり、堆肥を販売したりして、循環型の取り組みを進めています。また、近くのスーパーから廃棄する予定の食品を動物の餌として利用させていただいています。屠体給餌の取り組みとして、害獣で処分されるイノシシやシカなどの肉を肉食動物の餌に利用しています。
先ほどの話でもあった通り羽村市動物園の樹木も寿命が近いものが多く、二酸化炭素の吸収量が下がってきていると思うのですが、そんな中、他に動物園ができることについて、何か事例やヒントがあれば教えていただきたいです。
信時
CO2の吸収量を増やしていくためには、森林を健康的な状態に保つということが重要です。横浜市では、山梨県道志村にある横浜市の水源林を涵養しています。そして、横浜市民がその水を飲んでいるわけですが、そういった循環があることを知らしめるべく、クレジットを使った仕組みを作っています。つまり、横浜市内の企業、団体、個人などが寄付することで、森林整備を行い、その整備された森林から生まれた水を飲むことができるという循環ですね。森林を整えることによって、山から豊富で綺麗な水が出て、その水が川を通って海に流れる。そういう風に、海と山がつながり合い、循環しているということを意識すると、動物園ができることがたくさん見えてくると思います。動物園の取り組みと、水族館の取り組みをグループ内で連携させたら、より面白い活動ができ、大きな効果にもつながるのではないかと思います。
奥津
森林での活動も、ブルーカーボンにつながるということですね。海に流れ込む川をきれいにすることで、海洋ごみの量を減らしていく。グリーンカーボンとブルーカーボンをセットで考えていくことが大事かもしれませんね。

西武園ゆうえんち
高城 知宏
西武園ゆうえんち 遊園地ならではの取り組みを模索
―次に高城さんお願いします。
高城
西武園ゆうえんちは、数多くの昆虫等が生息する自然豊かな場所にあります。ただし、水族館や動物園と違い、海洋生物や動物の飼育業務を生業としていないため、環境への意識などが低く、他施設と比べてサステナ活動が遅れていると感じています。
そこで、私たちができることとして、園内の古い木を桜の木に植え替える活動や、伐採した木に生えている葉っぱを、羽村市動物公園の動物たちの餌にする活動などを行っています。他にも、遊園地の遊具を再利用して新しい遊び場を作ったり、取り壊した観覧車をフォトスポットとして残したりなどもしています。
ただ、私たちが「グリーンカーボン」のようなことをアピールしても、本当に意味があるのか、効果的なのか疑問に思っている部分はあります。遊園地ができるサステナビリティ活動について、良いアイデアがあれば教えてほしいです。
信時
伐採でいうと、公園の枯れ木で行うバイオマス発電なんかもありますよ。遊園地は子どもたちが多く訪れる場所でもあると思うので、教育の側面から、楽しみながらブルーカーボンについて学べる事業を、グループの他施設と連携して考えていくのはどうでしょうか。遊園地ならではのサステナビリティ活動ができるのではないかと思います。
奥津
西武園ゆうえんちは昭和の町を再現していますが、昭和の時代にサステナビリティ活動を行うならとか、面白くて分かりやすい形で伝えるのも良いかもしれないですね。園内の池にどんな生き物がいるのか調べて、子供たちに教えてあげたり、そんな活動も良いかもしれません。幅広くできることがあると思うので、一緒に考えていきましょう。
サステナビリティ活動を続けていくために

―本日は6施設のサステナビリティ活動について聞いてみました。今後も活動を続けていく、広げていくには、どのように進んでいけばよいのでしょうか。
信時
サステナ活動を遊び感覚で体験できるような仕組みを作ることで、多くの人を巻き込んだ取り組みができるようになるのではないかと思います。二酸化炭素(CO2)のクレジットを小さな単位で売買する仕組みを導入することで、子供たちでも気軽に環境保護に参加できるようになるかもしれません。例えば、100円や1000円といった少額でCO2削減に貢献できるような仕組みですね。コンビニで「CO2オフセット」できるサービスもあります。
動物園や水族館のような場所では、来園者が参加できるようなプログラムを実施することで、もっと多くの人に関心を持ってもらうことができそうですね。例えば、来園者が自分の行動によってどれだけCO2を削減できたか、ポイントで表示するようなシステムを導入したり。身近なところから誰でも参加できるものであることを知ってもらう活動をするのが良いのではないでしょうか。
―最後に奥津さんお願いします。
奥津
今日の座談会では、各施設でも役立つヒントがたくさん見つかったと思います。話を聞いて、改めて感じたのは、自分事として、自ら何ができるのか考えるということの大切さです。各々が自分のできることを考え、そこから一歩ずつ始めていけたらいいと思います。今後も新しい取り組みを進めていきましょう。


座談会の様子をより詳しくご覧になりたい方は、紙面をご覧ください。
座談会の様子をより詳しくご覧になりたい方は、紙面をご覧ください。






